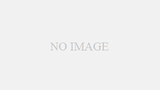皆さん、いりこだしを使ったことはありますか?
自分でだしをとることは少ないかもしれませんが、
一般的にはめんつゆやだし醤油によく使用されています。
また、鍋のスープにもよく使われますね。
今回はいりこだしについて詳しく説明していきたいと思います。
今回の記事では以下の点について説明します。
- いりことは?
- いりこは栄養が豊富
- どんな料理に使えるの?
- 正しいだしのとり方は?
- これらについて詳しく解説していきます。
いりことは?
小魚を煮てから乾燥させて作る水産加工品のことを「いりこ」と呼びます。
関西ではこの呼び名が一般的であり、関東では「煮干し」と呼ばれています。
したがって、「いりこ=煮干し」です。
いりこは主にだしをとる材料として使用され、そのまま乾煎りして食べることもあります。
最も一般的な原料はカタクチイワシですが、
マイワシ、うるめいわし、きびなご、アジ、トビウオ(あご)なども使用されています。
いりこは栄養が豊富
いりこには非常に豊富な栄養素が含まれています。
代表的なカルシウムをはじめとするミネラル類や、
魚特有の脂肪であるDHA、EPAなどの不飽和脂肪酸も豊富です。
ミネラル類
ミネラル類は生きるために必要な5大栄養素の一つです。
いりこに含まれるミネラル類には「カルシウム、鉄、亜鉛」が豊富に含まれています。
◯ カルシウム
カルシウムは骨や歯を丈夫に作る役割があります。
さらに、筋肉の収縮をサポートし、メンタル面でのケアも行います。
いりこには牛乳の約20倍のカルシウムが含まれていますが、
吸収が難しいため、カゼインを多く含む牛乳と組み合わせて摂取すると効果的です。
◯ 鉄
日本人に不足しがちな鉄分もいりこに豊富に含まれています。
手軽に摂取できるため、鉄分の補給源として優れています。
◯ 亜鉛
亜鉛はタンパク質の合成に関わる酵素の材料として重要なミネラルです。
新陳代謝やエネルギーの代謝、免疫機能の補助にも貢献します。
亜鉛が不足すると免疫機能が低下し、味覚障害などが発生する可能性があります。
不飽和脂肪酸
魚介類の脂肪は、様々な病気を予防するなど健康に良い影響を与えます。
不飽和脂肪酸は特に、中性脂肪やコレステロールの値を調整する働きがあります。
EPAやDHAなどが代表的な不飽和脂肪酸です。
これらはマグロ、イワシ、さんま、オリーブオイル、
ごま油、グレープシードオイルなどに多く含まれています。
いりこはだしに便利!
栄養価が高いいりこを「いりこだし」にすることで、
さまざまな料理に利用することができます。
おすすめの料理には以下があります。
- うどん
- ラーメン
- 炊き込みご飯
- チャーハン
- お鍋
- 和風パスタ
- お味噌汁
- 煮物
- 唐揚げ
いりこだしは和食だけでなく、中華料理にも使え、
パスタに組み合わせれば和風パスタにアレンジすることもできます。
いりこだしには鰹節の旨味成分であるイノシン酸が含まれており、
料理に深みを加えることができます。
いりこだしの取り方
次に、「いりこだし」を美味しくとるためのポイントについて説明します。
煮干しには旨味成分が豊富
なぜ煮干しから美味しいだしが出るのかご存知ですか?
鰹節や煮干しには「イノシン酸」といううまみ成分が豊富に含まれており、
特に煮干しからはたくさんのイノシン酸を抽出することができます。
煮干しからはアミノ酸系のペプチドも多く含まれ、
コクとまろやかさを同時に引き出すことができるため、和食に広く使用されています。
だしのとりかたは簡単
煮干しのだしのとりかたは様々で、おすすめの方法は「煮出し法」と「水出し法」です。
煮出し法:
定番のだしのとりかたで、同日に使いたい場合に選ばれます。
煮干しのクセが出ることがあり、味は水出し法の方が良いとされています。
水出し法:
煮干しを一晩水に浸けてゆっくり旨味を抽出する方法です。
クセがなく、上品な甘みのあるだしが取れますが、時間がかかります。
どちらの方法でも煮干しの旨味をしっかり引き出せますが、
急ぎで使いたい場合は煮出し法、
時間がある場合は煮干しのクセを抑えるために水出し法が適しています。
沸騰させないように注意
水出し法では前日から水に浸けておくだけでOKですが、
煮出し法では「沸騰させすぎると味が飛んでしまう」ため注意が必要です。
中火で煮込み、沸騰しそうになったら火を止め、水が黄金色になるのを待ちます。
約3分経過したら濾して完成です。
この方法は鰹節、昆布、干し椎茸などでも同じで、
「沸騰直前で火を止める」ことを覚えておくと良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では以下をまとめました。
- いりこは小魚を煮てから乾燥させて作る水産加工品
- いりこ=煮干し
- イノシン酸という旨味成分が豊富
- ミネラルや不飽和脂肪酸も多く含まれる
- 様々な料理に利用可能
- いりこだしの取り方は2種類あり、水出し法がオススメ
今回の記事ではいりこに関する様々な知識を紹介しました。
ぜひ日常のお料理の参考になさってください。