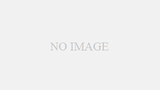夏になると、セミをよく見かけますね。
抜け殻を集めた思い出もありますよね。
でも、セミの幼虫には、地域ごとに異なる名前があるんですよ。
セミの幼虫の名前はなんでしょう?
ヤゴという言葉はトンボの幼虫を指すのはご存知でしょうが、セミの幼虫はどうでしょうか?
地域によって異なる呼び名があります。
北海道の多くの地域では「モズ」と呼ばれています。
また、北海道以外でも「モズ」と呼ぶ地域があります。
青森県や岩手県の一部では「ベコ」、山梨県や秋田県の一部では「ノコノコ」、
宮城県や東京都、兵庫県などでは「アナゼミ」と呼ばれます。
それ以外の地域でもさまざまな呼び名があります。
例えば、愛知県では「ドンゴロ」、
和歌山県では「ムク」や「ムクムク」、奈良県では「ウゴウゴ」と呼びます。
同じ県内でも、大阪府では「ゴンゴ」や「ウンゴロ」、
「ドンゴロ」、「オンゴロ」といった異なる呼び名があります。
地域ごとに異なる呼び名があるのは面白いですね。
セミの幼虫は羽化するまで何をしているのか?
セミの幼虫の呼び方についてご紹介しましたが、
次は幼虫が成虫になる過程についてお話します。
セミの種類によって異なりますが、ほとんどのセミは幼虫の時期を地中で過ごし、
成虫になってからの寿命は非常に短いと言われています。
幼虫として孵化してから、あのセミの姿に羽化するまで、
短いもので3年程度かかるものから、長いものでは17年ほどかかるものもいます。
都心部などでも一般的なアブラゼミでも、
成長には約6年かかると言われています。
地中での生活についてはまだ詳細が解明されていない点もあります。
何年もの長い期間、土の中で過ごすセミの幼虫ですが、
一体どのように過ごしているのでしょうか。
セミの幼虫はもちろん餌を摂取し成長していますが、
その餌は虫や微生物ではなく、木の根から得られる樹液です。
幼虫は木の根から樹液を吸い取り、その中の養分を摂取するために小さな穴と導管を使います。
しかし、幼虫の導管は小さく、一度に多くの養分を摂取することはできません。
そのため、長い時間をかけてじっと樹液を吸い続けながら成長します。
このように、土の中での成長によって、他の生物から攻撃を逃れつつ成長できるのです。
まとめ
夏に活動するセミの成虫は、その姿を見かける度に気軽に感じることがありますが、
実際には土の中で数年をかけて成長します。
地上に姿を現す前に地中での暮らしを送り、その成長過程は多様で興味深いものがあります。
夏の虫たちを注意深く観察してみれば、新たな発見が待っているかもしれません。