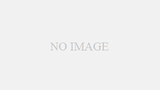青魚と言えば、サンマやサバが一般的に知られていますが、
他にもさまざまな種類が存在します。
この記事では、青魚の多様性とそれぞれの特徴を簡潔に紹介します。
また、「赤身魚」「白身魚」との違い、注意すべきアレルギー症状、
主要な栄養素とその効果についても解説します。
青魚の多様性と特徴一覧
通常、背中が青い魚が青魚として総称されます。
代表的な青魚のいくつかとその特徴について、以下で簡単にご紹介します。
サンマ科
-
- サンマ:体長約35cmの細長い魚で、柔らかくて脂ののりが良い。刺身や塩焼きに適しています。
サバ科
-
- マサバ:体長約50cmで皮付近の脂のりが良い。酢締めや塩焼き、味噌煮に適しています。
- サワラ:体長約1mで大型で淡泊であり、甘みがあり柔らかい。刺身や西京焼き向き。
- カツオ:体長1m以上の大型魚で血合いが多い。刺身やタタキに適しています。
- クロマグロ:体長3m以上の大型魚で、本マグロとも呼ばれます。主に刺身で食べられます。
- メバチマグロ:体長約2mで、クロマグロよりさっぱりしています。刺身向き。
アジ科
-
- マアジ:体長約30cmで脂ののりが良く、さっぱりした味わい。刺身やフライに適しています。
- ブリ:体長1mを超える大型魚で、身が赤くて脂のりが良い。刺身や煮魚、焼魚に適しています。
- カンパチ:大きなものでは1.8m以上になります。風味や食べ方はブリに似ています。
- ヒラマサ:見た目も味もブリに似ていますが、夏が旬の魚です。
ニシン科
-
- ニシン:体長約30cmほどの青魚で、卵は数の子。焼魚やニシン蕎麦(甘露煮)で食べられます。
- マイワシ:体長約20cmほどで血合いが多い。刺身や煮魚のほか、小魚は煮干しにもなります。
- キビナゴ:約10cmほどの小さな魚で、骨ごと食べられます。煮魚や揚げ物が美味しいです。
- コノシロ(コハダ):体長約30cmで、背の黒い水玉が特徴。江戸前寿司のネタとして有名です。
タチウオ科
-
- タチウオ:体長1.5m以上の細長い海蛇のような魚。クセがなく、刺身でも加熱しても美味しいです。
トビウオ科
-
- トビウオ:体長約35cmの細長い魚で、胸びれが大きい。クセがなく、刺身も加熱調理も美味しいです。
サヨリ科
-
- サヨリ:体長約30cmの細長い魚で、長い口が特徴。加熱すると風味が引き立ちます。
青魚の定義と「赤身魚」への分類の根拠
前述の青魚の種類を見て、「これが青魚なの?」と疑問に思った方もいることでしょう。
青魚とは具体的に何を指すのでしょうか。
その定義や、「赤身魚」に分類される理由について考えてみましょう。
青魚の定義:「背が青い魚の総称」
青魚は、その名の通り「背が青い魚」として総称されています。
ただし、外見での判別が主であるため、その定義は曖昧な部分もあります。
一般的に、魚は身の色に基づいて「赤身魚」「白身魚」の2つに分けられますが、
青魚は「赤身魚」に属します。
では、「赤身魚」と「白身魚」、そして「青魚」はどのように分類されているのでしょうか。
これについて、詳しく見ていきましょう。
分類の仕方
「青」という名前がついていますが、青魚は実は「赤身魚」に分類されています。
では、「赤身」と「白身」の分類基準は何でしょうか?
それは筋肉に含まれる「ミオグロビン(色素たんぱく)」の量です。
回遊魚ほど運動量が多く、そのためミオグロビン含有量も多くなります。
逆に、あまり動かない魚ほどミオグロビン量は少なくなります。
赤身魚の特徴
回遊魚は筋肉を動かすために酸素からエネルギーを合成します。
その際、筋肉に含まれるミオグロビンは鉄イオンを含み、
ヘモグロビンによって運ばれた酸素と結合します。
運動が多い魚ほど筋肉に酸素が多く必要とされ、ミオグロビン量が増え、赤みが強くなります。
青魚の特徴
「赤身魚」の中で、背が青い色をしているのが「青魚」です。
ただし、マグロやカツオは一般的に青魚とは呼ばれませんが、
これらはサバ科の魚であるため、「青魚」には分類されます。
白身魚の特徴
白身魚はミオグロビンが少なく、通常筋の比率が大きいです。
補食は俊敏ですが、普段は一箇所にとどまる生態のためエネルギー消費量が少ないです。
その結果、酸素の必要量も少なく、ミオグロビン量も少ないです。
代表的な白身魚にはタイ、カレイ、ヒラメ、サケ、フグなどがあります。
青魚とアレルギーの事象
青魚を摂取する際には、アレルギーに留意する必要があります。
サバなどの青魚を食べるとアレルギー症状が現れる場合があり、
青魚によるアレルギーの種類とその症状について見ていきましょう。
青魚によるアレルギー反応は主に3種類あります。
魚肉によるアレルギー
魚肉そのものがアレルギーの原因となり、
魚肉を摂取するとアレルギー反応が現れることがあります。
アニサキス症
魚肉に寄生しているアニサキスによるアレルギーはよく知られています。
ただし、魚肉自体がアレルギーの原因ではなく、
アニサキスが存在しなければアレルギー反応は起こりません。
ヒスタミン食中毒
ヒスタミンは青魚(赤身魚)に含まれるヒスチジンというアミノ酸から生成されます。
特に青魚を室温で放置すると、菌が繁殖してヒスタミンが生成されやすくなります。
そのため注意が必要です。
ヒスタミン中毒の症状は比較的軽度で、
じんましんや顔面の紅潮、頭痛、発熱などが主なものです。
重症な場合は医師の診断が必要で、抗ヒスタミン剤が処方されることがあります。
ヒスタミンの生成を抑えるため、魚を冷蔵庫で保管し、適切に調理することが重要です。
青魚に含まれる主な栄養の種類とその効果
最後に、青魚に含まれる主な栄養素とその期待される効果について紹介します。
EPAとDHA
EPAとDHAはいずれも必須脂肪酸で、
「n-3系脂肪酸(またはオメガ3系)」と呼ばれます。
これらは血液をサラサラにし、中性脂肪やコレステロールを抑制する効果が期待されています。
食事からの摂取が必要で、サプリメントも利用されます。
アンセリン
魚肉に多く含まれるアンセリンは抗酸化作用などが期待されています。
青魚は筋肉量が多いため、アンセリン含有量も多い特徴があります。
タウリン
タウリンはコレステロールや中性脂肪を減少させる効果が期待されます。
また、血圧の調整や肝臓の解毒機能を強化すると言われています。
水溶性なので、煮たり茹でたりする際には汁ごと摂取すると良いでしょう。
分岐鎖アミノ酸
バリン、ロイシン、イソロイシンの3つのアミノ酸は分岐鎖アミノ酸と呼ばれます。
これらは人体では生成できない必須アミノ酸であり、
持久力向上や筋肉痛の軽減などの効果が期待されています。
まとめ
青魚は赤身魚の一種であり、さまざまな種類が存在します。
同じ青魚でも特徴が異なるため、幅広く楽しむことができます。
アレルギーに関しては、青魚自体が原因である場合もありますが、
アニサキスやヒスタミンが引き起こす場合は適切な予防が可能です。
消費期限を守り、適切な管理下で美味しくいただきましょう。